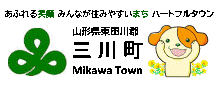令和6年度 国民健康保険税について
更新日:2024年6月11日
国民健康保険税のあらまし
国民健康保険税(国保税)は、会社などの健康保険(健康保険、船員保険、後期高齢者医療制度など)に加入していない方を対象に医療の給付等を行うことを目的とした国民健康保険事業(国保)に充てるため、地方税法に基づき課税する税金です。
町内にお住まいの方で、他の健康保険に加入しているか生活保護を受けている方以外は、国保に加入しなければなりません。
国保税の納税義務者は世帯主です。世帯主が被保険者(加入者)でない場合でも、世帯員に国保の被保険者がいれば、世帯主に国保税が課税されます。
国保税は国保制度の運営に欠かせない大切な財源です。皆さま一人ひとりが国保税を納めることで、大きな病気やけがをしたときに安心して医療が受けられます。だれもが安心して医療を受けられるようにするため、国保税を納付くださるようお願いいたします。
令和6年度の国民健康保険税の納税通知書は7月中旬に郵送でお知らせします。
令和6年度国民健康保険税
1.税率(額)及び課税限度額
| 医療給付費分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護納付金分 | |
|---|---|---|---|
| 所得割率 | 6.56% | 2.84% | 2.40% |
| 均等割額 | 28,000円 | 11,800円 | 12,000円 |
| 平等割額 | 19,200円 | 8,000円 | 6,000円 |
| 課税限度額 | 65万円 | 24万円(改正前:22万円) | 17万円 |
2.軽減判定所得
| 軽減割合 | 改正前(令和5年度) | 改正後(令和6年度) |
|---|---|---|
| 7割軽減基準額 | 43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1) | 43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1) |
| 5割軽減基準額 | 43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1) | 43万円+(29万5千円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1) |
| 2割軽減基準額 | 43万円+(53万5千円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1) | 43万円+(54万5千円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1) |
具体的な計算方法
次の1~3を合算した額(100円未満切捨て)が、令和6年度の年税額となります。介護納付金分については、世帯に介護保険第2号被保険者(40歳から64歳の被保険者)がいる場合に計算します。
1.医療給付費分 【次の(1)から(3)までの合計額】 (課税限度額:65万円)
(1)所得割額 ((前年中の総所得額等-430,000円)×6.56%)を被保険者ごとに計算した合計額
(2)被保険者均等割額 被保険者数×28,000円
(3)世帯別平等割額 一世帯19,200円
2.後期高齢者支援金等分 【次の(1)から(3)までの合計額】(課税限度額:24万円)
(1)所得割額 ((前年中の総所得額等-430,000円)×2.84%)を被保険者ごとに計算した合計額
(2)被保険者均等割額 被保険者数×11,800円
(3)世帯別平等割額 一世帯8,000円
3.介護納付金分 【次の(1)から(3)までの合計額】(課税限度額:17万円)
(1)所得割額 ((前年中の総所得額等-430,000円)×2.40%)を第2号被保険者の被保険者ごとに計算した合計額
(2)被保険者均等割額 第2号被保険者の被保険者数×12,000円
(3)世帯別平等割額 一世帯6,000円
税の軽減等
1.基準よりも所得が少ない世帯に対する軽減
世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額等の合算額が以下の表の軽減判定所得に該当する場合、均等割額と平等割額がそれぞれの軽減割合で軽減されます。
| 軽減割合 | 軽減判定所得 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 |
| 5割軽減 | 43万円+(29万5千円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 |
| 2割軽減 | 43万円+(54万5千円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 |
※世帯に特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度に移行する直前の医療保険が国保で、かつ、その前後で世帯主が同じ方)がいる場合は、その人数と所得も含めて判定します。
※軽減判定所得は、譲渡所得は特別控除前の金額、営業や農業等は専従者控除前の金額で算定します。
※65歳以上の方の年金所得は、15万円を控除した後の金額が軽減判定の対象となります。
※所得税または町県民税(国保税)の申告義務のある被保険者が申告をしていない場合は、軽減の対象になりません。
2.未就学児の被保険者均等割額の減額
令和4年度分以降の国保税について、国保に加入している未就学児(小学校就学前の子ども)分の均等割額の5割が減額されます。
なお、基準よりも所得が少ない世帯(2割・5割・7割軽減)に該当する場合は、軽減適用後の金額が2分の1に減額されます。
3.後期高齢者医療制度導入に係る激変緩和措置
1. 国保から後期高齢者医療制度へ移行する被保険者がいる場合、国保税の負担が急に増えることがないように、次の軽減策がとられています。
(1)所得の少ない世帯に対する国保税の軽減について
国保税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、5年間今までと同じ軽減を受けることができます。
(2)世帯別平等割額の軽減について
国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、国保の被保険者が一人となる場合は5年間世帯別平等割が半額になります。
2. 75歳以上の方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳から74歳)が新たに国保に加入する場合、申請により被保険者に係る所得割額が賦課されず、被保険者均等割額が半額に、さらに、被保険者が1人の場合は世帯別平等割額が半額になります。
4.非自発的失業者に対する軽減措置(倒産や解雇など会社都合の退職等)
次に該当する方は、失業時から翌年度末までの間、前年中の給与所得を100分の30として計算します。
ただし、離職時点で65歳未満の方が対象で、軽減を受けるには役場町民課での手続きが必要です。
- 雇用保険の特定受給資格者(「雇用保険受給資格者証」離職理由コード11.12.21.22.31.32の方)
- 雇用保険の特定理由離職者(「雇用保険受給資格者証」離職理由コード22.33.34の方)
5.産前産後期間の軽減措置
国民健康保険に加入されている方で、出産予定の方又は出産された方は、産前産後の一定期間、国民健康保険税の所得割と均等割が免除される制度があります。詳しくは下記のページからご確認ください。
納付方法について
1. 普通徴収
7月から翌年3月までの毎月月末、年9回の納期になります。(各期別の税額は、年税額を納付回数で割った後、次回以降の各期の1,000円未満の端数を最初の納期額に合算します。)
納付方法は、口座振替または納付書になります。
2. 特別徴収
年金の支給月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に差し引かれます。
次の(1)から(3)までの全てに該当する方が、年金特徴に切り替わります。
(1)世帯主が被保険者になっていること。
(2)世帯内の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること。
(3)特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国保税と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1を超えないこと。
※年金からの特別徴収については、申し出によって口座振替による納付に変更することができます。
年度の途中で、被保険者の資格を取得し、または喪失した場合
被保険者の資格を取得した場合、取得した月から国保税を計算して納付していただきます。遅れて届出した場合は、さかのぼって計算します。また、喪失した場合は、月割りで再計算します。
災害などの特別の事情がなく国保税を滞納すると
災害などの特別の事情がなく国保税を滞納すると、次のような措置が講じられますのでご注意ください。
- 督促による督促手数料や延滞金が、加算される場合があります。
- 9カ月以上滞納すると、有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
- 1年以上滞納すると、保険証を返却していただくとともに、「被保険者資格証明書」が交付される場合があります。この場合、医療費は医療機関等の窓口でいったん全額を支払い、後日、役場町民課に申請書類を提出することにより、保険給付分(7割又は8割)が払い戻されます。(「短期被保険者証」または「被保険者資格証明書」が交付された方で、国保税を完納されたなどの場合は、「被保険者証」が交付されます。)
- 1年6カ月以上滞納すると保険給付の全額または一部の支払いが一時的に差し止められます。
問い合わせ先
- 町民課 税務係
- 〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
- 電話:0235-35-7026
- FAX:0235-66-3139