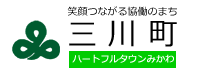
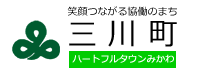
国民健康保険の医療費が高額になったとき
同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担額を超えた場合、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
自己負担額の計算条件(70歳未満の人の場合)
(1)暦月(1日から末日)ごとに計算します。
(2)同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算になります。
(3)2つ以上の医療機関にかかった場合には別計算になります。
(4)入院時の食事代や差額ベット代など保険適用外の医療行為は対象外です。
世帯の医療費を合算して限度額を超えたとき
同一世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が、申請によりあとから支給されます。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請
医療機関の窓口での支払いは、「限度額適用認定証」を提示することにより、自己負担限度額までとなります。なお、あらかじめ町民課国保係に認定証の交付を申請することが必要となります(国保税を滞納していると交付されない場合があります)。
また、オの区分(住民税非課税世帯)の人が入院したときは、入院前に町民課国保係に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けると食事代の負担が軽減されます。
70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)の限度額を適用したあとに、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
自己負担額の計算条件(70歳以上75歳未満の人の場合)
(1)暦月(1日から末日)ごとに計算します。
(2)外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担額は世帯単位で合算します。
(3)病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算します。
(4)入院時の食事代や、差額ベット代など保険適用外の医療行為は対象外です。
75歳になる月の自己負担限度額について
75歳に到達する月は、誕生日前の国保と、誕生日後の後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれぞれ本来の額の2分の1ずつになります。
70歳未満と、70歳以上75歳未満の人が同一世帯の場合
70歳未満と、70歳以上75歳未満の人が同一世帯にいる場合も、合算することができます。
(1)まず70歳以上75歳未満の人について個人単位の限度額を適用し、次に70歳以上75歳未満の人の世帯単位の限度額を計算します。
(2)70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額と(1)で計算した額を合計し、70歳未満の人の所得区分の自己負担限度額を適用します。
手続きの流れ
国保では、診療を受けた月の2か月後をめどに高額療養費申請のお知らせを郵送します。お知らせが届きましたら、町民課国保係で申請してください。診療月の翌月1日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
手続きに必要なもの
医療費が高額になった世帯に、介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後、合算して一定の限度額(年額 8月から翌年7月)を超えた場合は、申請により超えた分があとから高額介護合算療養費として支給されます。
国保の加入者で、申請の必要な世帯にお知らせをしていますので、お知らせが届きましたら町民課国保係で必ず申請をしてください。
ご注意ください。
8月から翌年7月までの計算期間中に転入や転出、加入する健康保険が変わった場合は、8月から翌年7月までの年間の自己負担が把握できないため、お知らせできません。お手元の医療や介護の領収書などで判断し、申請する必要がありますのでご注意ください。ご不明な場合は、町民課国保係にお問い合わせください。
長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を発行しますので、町民課国保係に申請してください。自己負担限度額が1医療機関につき、1か月10,000円となります。
厚生労働大臣指定の特定疾病
住所:〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7027・7028 ファックス:0235-66-3139